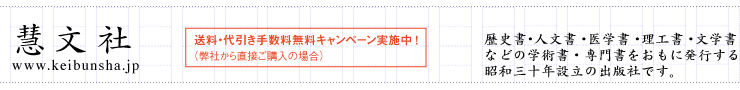|
推薦の辞:
白川ゆうきの小説は、一行目から心が震え出す。言葉に対する絶対的な姿勢に感動するからだ。──江上剛(作家)
「白川ゆうきの独創は、不器用な愛にのたうつ人たちに一種の崇高さを添えたことだ。」
──髙橋昌男(作家)
圭一はスコップが重く、まだ思うように消し粉をかけられない。いつ怒られるかとびくついていたが、源造は黙々と作業を続けるばかりであった。圭一は、めっきり口数の少なくなった源造をみて、こんなとき綾乃がいるといいのにと思った。しかしすぐ、もう綾乃は山にこないかもしれないと思いなおし、暗い気持になった。綾乃は、とうちゃんには内緒だよといって、夜も食堂に勤めていたのだった。
「ほうれ、いい音だ。鋼鉄並みの堅炭よ」
すっかり冷めていない炭をぶっつけあわせて、源造は汗で黒く光った顔をしわくちゃにした。澄んだ音が木立のあいだを渡った。(「蔵王おろし」)
|